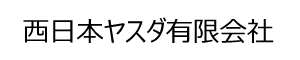公的年金制度の仕組みと意義について
日本では少子高齢化が進むなか、自身の老後生活に不安を抱く方も多いでしょう。そんな不安を支える柱の1つが「公的年金制度」です。
年金と聞くと、老後の生活資金を思い浮かべる方が多いかもしれませんが、実際にはそれだけではありません。病気やケガで障害を負ったとき、一家の働き手が亡くなったときなど、人生のリスクにも備えるための制度です。
この記事では、公的年金制度の基本的な仕組みと社会的意義について、わかりやすく解説します。
公的年金制度の仕組み
日本の年金制度は、「国民皆年金」の原則に基づき、20歳以上60歳未満の全国民が加入対象です。
建物の構造に例えて「2階建て」と表現され、1階部分はすべての人が加入する「国民年金(基礎年金)」、2階部分が会社員や公務員向けの「厚生年金」となります。
加入者は以下の3種類に分類されます。
・第1号被保険者:自営業者、学生、フリーランスなど。保険料は本人が納付する。
・第2号被保険者:会社員や公務員など。保険料は給与から天引きされ、事業主と折半で納付される。
・第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている配偶者など。保険料の個別負担は不要。
さらに、任意で加入できる「私的年金(例:iDeCo、企業年金など)」が3階部分として存在し、公的年金に上乗せする形で老後資金を補完できます。
公的年金制度の意義と主な給付内容
公的年金制度は「賦課方式」により、現役世代が支払う保険料を、今の受給者に給付する「世代間の支え合い」の仕組みで運営されています。これにより、インフレなどの経済変動に柔軟に対応できるのが特徴です。
主な給付は以下の3つです。
・老齢年金:原則65歳から受給可能。受給開始年齢を60~70歳の間で選択でき、保険料納付期間が10年以上あることが受給条件。
・障害年金:病気やケガで障害を負った際に支給される。初診日に加入していた制度によって「障害基礎年金」または「障害厚生年金」が適用される。
・遺族年金:加入者や受給者が亡くなった際、その遺族に支給される年金。家計を支えていた人の死亡に備える制度の1つ。
まとめ
公的年金制度は、すべての人が加入し、保険料を納めることで支えられる社会の基盤です。老後だけでなく、病気・障害・死亡といった予期せぬ事態にも備えられる、きわめて重要な仕組みといえるでしょう。
ご自身の年金加入状況や将来の見込額は、「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で確認できます。ぜひ一度チェックして、安心できる将来設計にお役立てください。