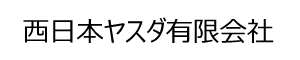公的年金制度の歴史について
私たちの老後生活を支える重要な仕組みが、公的年金制度です。しかしその内容や成り立ちは、意外と知られていないものです。
年金制度は、社会や経済の変化に合わせて幾度となく見直されてきました。その変遷を知ることで、制度の意義や目的をより深く理解できるようになります。
この記事では、日本の公的年金制度がどのように始まり、現在の形に至ったのか、その歴史の大きな流れをわかりやすくご紹介します。
公的年金制度の始まりと「国民皆年金」の実現
日本の公的年金制度は、「労働者年金保険法」が制定された翌年の1942年から実施されています。これは主に民間の会社員や公務員等を対象としたもので、当時の対象者は限定的でした。
その後、戦後の復興とともに社会保障の整備が進められ、1961年に「国民年金法」が施行されます。これにより、自営業者や農業従事者、漁業者など、会社員以外の人々も含めた全国民が年金制度に加入する「国民皆年金」が実現しました。対象は20歳以上60歳未満のすべての国民であり、日本における年金制度の転換点となりました。
この制度の導入によって、職業や雇用形態に関係なく、誰もが老後の生活に備えることができる基礎が整ったのです。
2階建ての「基礎年金制度」の始まり
国民皆年金の導入は大きな前進でしたが、高齢社会の到来に備えて1985年、全国民に共通の「基礎年金」を支給する仕組みがスタートします。これが、現在の「2階建て」年金制度の始まりです。
1階部分は、すべての人が加入する「国民年金(基礎年金)」で、老後の生活における基礎部分の保障を担います。当時の2階部分は、会社員や公務員が加入する「厚生年金」や「共済年金」で、基礎年金に上乗せする形で支給されました。
その後も少子高齢化の進行や働き方の多様化に対応するため、支給開始年齢の引き上げ、年金額の見直し、パートや非正規労働者への適用拡大など、制度は絶えず見直されているのです。
まとめ
日本の公的年金制度は、限られた労働者だけを対象とした制度から、すべての国民が支え合う「国民皆年金」へと発展しました。さらに、1985年の制度改革を経て、全員に共通する「基礎年金」と、職業による上乗せ部分を組み合わせた「2階建て」の構造が確立。
このように公的年金制度は、社会の変化に応じて柔軟に変化を重ねてきた社会保障の要です。今後も高齢化の進行や労働環境の変化に応じて、制度の持続可能性と公平性を確保するための見直しが行われていくでしょう。
年金制度の仕組みとその背景を理解することは、私たち一人ひとりが将来に備えるための大切な第一歩なのです。