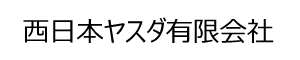遺族年金について
一家の働き手に万が一のことがあった場合、残された家族の生活はどうなるのか、という不安は誰にでもあるものです。
そのようなときに、家族の生活を経済的に支えるための公的な仕組みが「遺族年金」制度です。
本記事では「遺族年金」の基本的な仕組みや種類、対象者について、わかりやすく解説します。
遺族年金とは、どんな制度?
遺族年金とは、国民年金または厚生年金保険の被保険者(または被保険者だった方)が亡くなった際に、その方によって生計を維持されていた遺族が受け取れる年金です。
これは、亡くなった方が納めてきた保険料を元に、残された家族の生活を支えることを目的としています。
遺族年金には、亡くなった方の年金の加入状況に応じて、主に「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2つの種類があり、条件によっては両方を受け取れる場合もあります。
2つの遺族年金|その違いと対象者
遺族年金は、大きく2つの制度に分かれています。
それぞれ誰が対象になるのか、基本的な違いを見ていきましょう。
遺族基礎年金
遺族基礎年金は、国民年金の第1号被保険者だった方が亡くなった場合に支給される制度です。
この年金を受け取れるのは、亡くなった方に生計を維持されていた「18歳年度末までの子(障害等級1級・2級の場合は、20歳未満の子)がいる配偶者」または「子」に限られます。
したがって、お子さんがいない配偶者の方は、この遺族基礎年金を受け取ることはできません。
遺族厚生年金
こちらは、会社員や公務員など、厚生年金に加入していた方が亡くなった場合に支給される遺族年金です。
遺族基礎年金が支給される対象の方は、それに上乗せする形でこの遺族厚生年金が支給されます。
遺族厚生年金の対象となる遺族の範囲は広く、子のいない配偶者や、一定の条件下では父母、孫、祖父母も対象となります。
ただし、遺族の中で最も優先順位が高い方が受け取ることになります。
一般的には、配偶者が最も優先されるようです。
例えば、夫が亡くなった場合、30歳未満で子のいない妻は5年間の有期給付となるなど、年齢や子の有無によって給付内容が変わる点には注意が必要です。
まとめ
遺族年金は、予期せぬ出来事によって家計の支え手を失った家族にとって、その後の生活を再建するための非常に重要な制度です。
自分がどの年金に加入しているかによって、万が一の際に家族が受け取れる遺族年金の種類や額が変わってきます。
自営業の方は「遺族基礎年金」、会社員や公務員の方は「遺族厚生年金」が基本となります。
それぞれの制度で対象となる遺族の範囲や受給要件が異なるため、ご自身の状況と照らし合わせて理解しておくことが大切です。
より詳細な受給資格や手続き、具体的な年金額については、日本年金機構のウェブサイトを確認したり、年金事務所や専門家に相談したりすることをおすすめします。