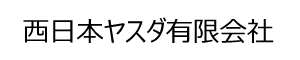障害年金について
病気やけがによって、これまで通りの仕事ができなくなったり、日常生活に支障をきたしたりすることがあります。この場合に利用できる公的支援制度が「障害年金」です。
老後に受け取る「老齢年金」とは異なり、働き盛りの世代でも対象となることから、暮らしを守る大切な制度といえます。
この記事では、障害年金の基本的な仕組みと受給条件について、わかりやすく解説します。
障害年金の基本的な仕組み
障害年金とは、公的年金制度に加入している人が、病気やけがにより障害の状態になった場合に受け取れる年金です。
その目的は、障害によって働くことが難しくなり収入が減ったり、生活に支障が出たりした際に、本人とその家族の経済的負担を軽減することにあります。
障害年金には、以下の2つの種類があります。
・障害基礎年金:初診日に「国民年金」に加入していた人が対象
・障害厚生年金:初診日に「厚生年金」に加入していた人が対象
ここでの「初診日」とは、障害の原因となる病気やけがで、初めて医師の診察を受けた日を指します。
どちらの年金を受け取れるかは、この初診日に加入していた年金制度によって決まるのです。
障害年金を受け取るための3つの条件
障害年金を受け取るためには、以下の3つの条件をすべて満たしている必要があります。
・初診日の要件
・保険料納付の要件
・障害の程度の要件
まず、初診日の要件として、障害の原因となった病気やけがで初めて医師の診療を受けた日が、国民年金または厚生年金の加入期間中でなければなりません。
次に、保険料納付の要件では、初診日の前日時点で一定期間、年金保険料を納めていることが求められます。
未納期間が多いと、たとえ障害の程度が重くても受給できない可能性があるため注意しましょう。
そして、障害の程度の要件として、障害の状態が国の定める障害等級(1級または2級など)に該当する必要があります。
障害等級は、日常生活への支障や就労能力の低下の程度によって認定されます。
まとめ
障害年金は、思わぬ病気やけがで生活が困難になった際に、経済的に暮らしを支えてくれる大切な公的制度です。
「初診日」「保険料納付の状況」「障害の程度」の3つの条件を満たす必要があります。
自分や家族が対象となる可能性がある場合は、早めに確認・相談することが重要です。
日本年金機構の「ねんきんダイヤル」や年金事務所、または社会保険労務士などの専門家に相談することで、正確な情報や手続きを知ることができます。
制度を正しく理解し、いざという時に備えることは、私たち自身の暮らしと安心を守る第一歩といえるでしょう。